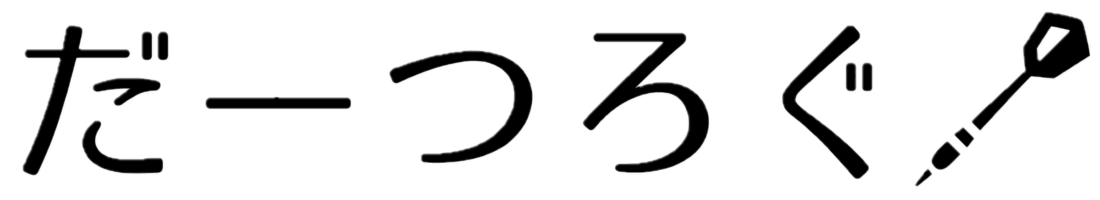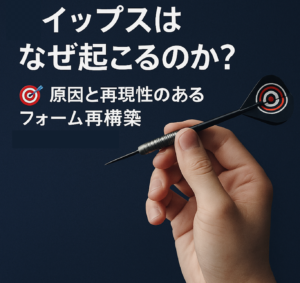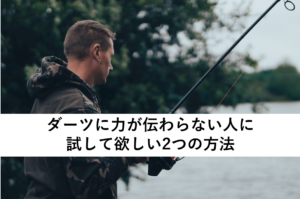当ブログでは、アフィリエイト広告を使用しており、記事内に広告が含まれる場合があります。
はじめに
「なぜか、投げられない…」
いつも通りセットアップし、テイクバックも問題ない。
でも、いざリリースの瞬間に腕が固まり、ダーツが指から離れない。
「これはイップスなのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
また、長年染み付いていたはずのスローが突然ぎこちなくなったり、プレッシャーのかかる場面で思い通りに投げられなくなったりしたことはないですか?
これは、「イップス(Yips)」と呼ばれる現象で、スポーツ選手や音楽家にも見られる神経系の問題です。
この症状は、単なるスランプではなく、脳の運動制御システムの異常や心理的ストレスの影響を受ける可能性があります。
特に、ダーツ界のレジェンド エリック・ブリストウ がこの症状に苦しみ、一時的に競技から遠ざかったこともあるそうです。
この記事では、「イップスとは何か?」、「局所ジストニアとの違い」、「どのように克服すればいいのか?」を解剖学・神経学・心理学の視点から解説します。
イップスのチェックリスト
以下の症状に当てはまる場合、イップスの可能性があります。
- 投げる瞬間に腕が言うことを聞かない
- 構えやテイクバックは問題ないのに、リリースのタイミングで腕が硬直する。
- ダーツが指から離れない、または無意識に変な方向に飛んでしまう。
- 動作がぎこちなくなる
- 以前は自然にできていたフォームが突然崩れ、ターゲットから大きく外れる。
- 練習では問題ないのに、試合では極端にミスをする。
- 極度の違和感や緊張を感じる
- 手首や指に力が入りすぎて震えたり、体が不自然にこわばったりする。
- 単なる試合前の緊張とは異なり、特定の動作をするときだけ異常な感覚が続く。
- ダーツ以外の動作では問題がない
- 日常生活ではペンを握ったり、箸を使ったりするのに支障がない。
- 他のスポーツでは問題なく動作ができるが、ダーツを投げるときだけ不調が出る。
イップスの原因—解剖学・神経学・心理学の視点から
イップスと局所ジストニアの違い
イップス(Yips)
- 心理的ストレスやプレッシャーが原因で、無意識のうちにスムーズな動作ができなくなる現象。
- 試合などのプレッシャーのかかる場面で発症しやすく、緊張や焦りがトリガーになることが多い。
- 意識すればするほど悪化する傾向があり、「力を抜こう」と思っても抜けないことが特徴。
- 練習では問題ないが、本番で動作が崩れることが多い。
- 脳の「運動プログラム」が誤作動を起こし、一時的に正常な動作が難しくなる。
局所ジストニア(Focal Dystonia)
- 脳の運動制御システム(基底核・感覚運動皮質)の異常による不随意運動。
- ダーツだけでなく、ピアニスト、ゴルファー、テニス選手など、特定の動作を繰り返す競技者にも発症する。
- 長年の反復動作が引き金となるため、慢性的に進行するケースがある。
- 症状が慢性化すると、自分の意思とは無関係に腕や指がこわばる。
- イップスと異なり、発症すると「意識しても修正できない」ケースが多く、神経学的な治療が必要。

ダーツのイップス・ジストニアの改善策|リハビリと治療法
(1) 神経リハビリ(感覚再学習)|局所ジストニア向け
✅ ミラーセラピー(鏡療法)
ミラーセラピーは、健康な手の動きを鏡で映し、それを脳に学習させることで、脳の運動マッピングをリセットし、誤った運動回路を修正するリハビリ手法です。
主に神経リハビリテーションの分野で用いられ、脳卒中や局所ジストニアの治療に活用されています。
実践方法
- 鏡を体の中央に置き、健康な手を鏡に映すように配置する。
- 健康な手をゆっくりと動かし、それを「患部の手」として脳に認識させる。
- 1日10〜15分、意識して続けることで、神経回路の誤作動をリセットする効果がある。
💡 この方法は、特に局所ジストニアの患者向けで、理学療法士や作業療法士がいる神経リハビリ専門の施設で指導を受けるとより効果的です。
✅ バイオフィードバック訓練
バイオフィードバックは、筋電図(EMG)などを用いて筋肉の活動を可視化し、患者が自分の筋緊張を認識しながら制御する訓練です。
これにより、不随意な筋収縮を抑えたり、適切なリリースタイミングを取り戻すことができます。
スポーツクリニックや理学療法クリニックで提供されることが多いです。
✅ 感覚統合トレーニング(異なる手で投げる、フォーム変更)
神経の誤作動をリセットするため、普段とは異なる手や異なるスタイルで投げるトレーニングを行います。
これにより、脳が新たな運動パターンを学習し、異常な動作を修正しやすくなります。
スポーツトレーナーや神経リハビリ専門の施設で指導を受けると効果的です。
(2) フォームの再構築
✅ 逆手で投げる(運動マッピングのリセット)
- イップスやジストニアの影響を受ける手とは逆の手で投げることで、脳の運動プログラムをリセットする効果がある。
- 本来の投げ方を無意識にしようとする動作を防ぎ、新しい運動回路を作るのに役立つ。
- 最初は違和感があるが、「逆手で狙う」という動作を繰り返すことで、脳の過剰な制御を抑えることができる。
非利き手の使用は、運動学習を促進する」とする研究もあり、実践することで神経系の適応能力を高める効果が期待できます!
✅ テイクバックのスピードを変えてみる
異なるスピードで動作を行うことで、新しい運動パターンを脳に定着させる。
✅ リズムを変えてスローする(リズムトレーニング)
- 脳の運動制御回路を再調整するために、リズムを変えて投げるのが有効。
- メトロノームアプリを使い、「速め」「ゆっくり」のリズムでスローする。
- 「1、2、3…」とカウントしながら投げることで、無意識の力みを抑える。
実践方法:
- リズムが乱れないように、一定のペースで練習する。
- 通常のスローを録画し、リズムを確認する。
- 一定のリズムで投げるように意識する(メトロノームアプリ推奨)。

(3) 神経調整・治療
✅ ボツリヌス毒素(ボトックス)注射
ボツリヌス毒素(ボトックス)を局所的に注射することで、過剰に緊張した筋肉を一時的に弛緩させる治療法です。
ジストニアの治療に効果があり、筋肉の異常収縮を抑制することで症状を軽減します。
神経内科や整形外科の専門クリニックで受けることができます。
✅ 理学療法(フィジオセラピー)
理学療法士による手技療法や運動療法で、過剰に緊張した筋肉をほぐし、適切な筋肉の使い方を学びます。
ジストニアの症状がある場合、特定のリハビリメニューが組まれることが多いです。
整形外科やスポーツリハビリ施設で受けられます。
| 分類 | メカニズム | 主な症状 | 発症の原因 | 治療・改善方法 |
|---|
| イップス | 心理的要因と神経系の誤作動 | 緊張・不安・過度な意識による動作の硬直・ぎこちなさ | ストレス、失敗のトラウマ、過剰な意識 | メンタルトレーニング、ルーティンの確立、フォームの調整 |
| 局所ジストニア | 脳の運動制御システムの異常 | 無意識の筋肉の収縮、異常な動作パターンの固定化 | 過度な反復動作、感覚運動マッピングの異常 | フォームの再学習、感覚リハビリ、ボトックス療法 |
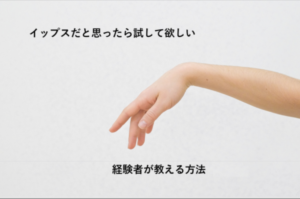
最後に—イップスは克服できる
イップスや局所ジストニアと向き合うのは、決して簡単なことではありません。
「なぜ自分だけがこんな目に…」と思ったことがあるかもしれません。
「努力しているのに、結果がついてこない」と何度も悔しい思いをしたかもしれません。
私自身もグリップイップスやイップスを何年も続け、苦しみを経験しました。
「いくら頑張っても治らないのでは?」という不安、何をしても改善しない絶望感… それでも、諦めなかったからこそ、今ここに立っていることができています。
焦らず、ゆっくりでもいい。 一歩ずつ、自分のペースで進んでいきましょう。
適切な治療やトレーニングを受けることで、症状を軽減し、再びスムーズにダーツを投げられる可能性があります。
神経内科、理学療法士がいるクリニック、スポーツリハビリ施設を活用し、専門的なサポートを受けることが大切です。
あなたが今、苦しんでいることは「あなたが弱いから」ではなく、 それだけ真剣にダーツに向き合ってきた証拠 です。
試行錯誤しながら自分に合う方法を見つけ、 ダーツを楽しむ気持ちを取り戻せる日が必ず来ます。
「もう一度、思い通りに投げられる日は必ず来る」
あなたの努力は無駄にならない。 諦めなければ、前に進める!
私はそう思っています。一緒に頑張りましょう!

この記事が参考になったら、SNSでシェアやコメントをお願いします!
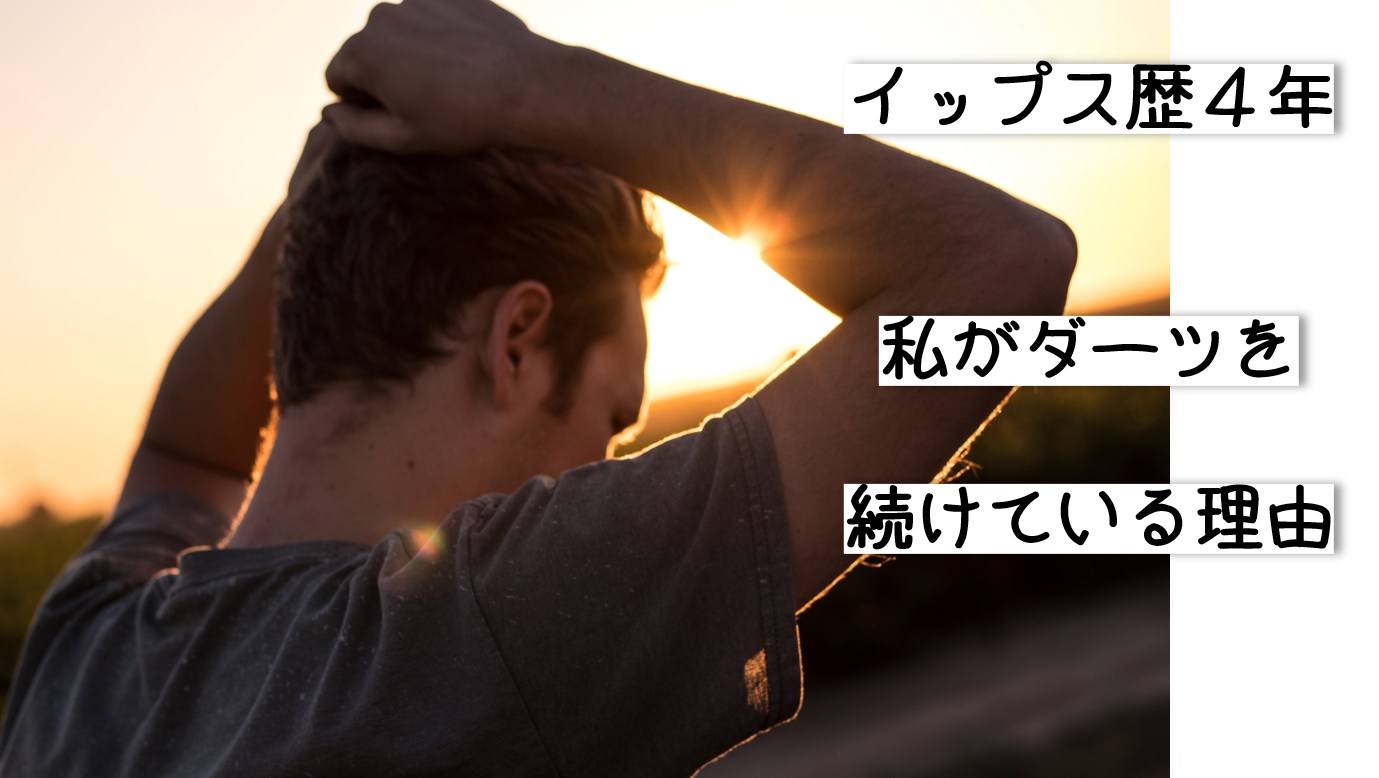
消耗品などの買い忘れはありませんか?
参考文献・論文
※私は学者や医者ではありません。
調べた情報を元に記載、解釈した内容を記載しております。
解釈の間違いなどある可能性があることをご了承ください。
- イップスのメカニズムに関する研究
- Smith, A. M., & Adler, C. H. (2019). “Yips and Focal Dystonia in Athletes: A Review.” Sports Medicine, 49(2), 181–193. DOI: 10.1007/s40279-018-1069-5.
- Altenmüller, E., & Jabusch, H. C. (2010). “Focal Dystonia in Musicians: Pathophysiology and Therapy.” Advances in Neurology, 111, 293–300. (音楽家の局所ジストニアに関する総説)
- 神経学的アプローチと治療法
- Hallett, M. (2006). “Pathophysiology of Dystonia.” J. Neural Transm. (Suppl.) 70, 485–488. DOI: 10.1007/978-3-211-45295-0_72.
- Quartarone, A., & Hallett, M. (2013). “Emerging Concepts in the Physiological Basis of Dystonia.” Movement Disorders, 28(7), 958–967. DOI: 10.1002/mds.25532.
- ボツリヌス療法とリハビリの有効性
- Jankovic, J. (2004). “Botulinum Toxin in Clinical Practice.” Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75(7), 951–957. DOI: 10.1136/jnnp.2003.034702.
- Zeuner, K. E., & Hallett, M. (2003). “Sensory Training as Treatment for Focal Hand Dystonia.” Current Neurology and Neuroscience Reports, 3(4), 291–296.
- メンタル的要因とイップス克服法
- Baumeister, R. F. (1984). “Choking Under Pressure: Self-Consciousness and Paradoxical Effects of Incentives on Skillful Performance.” Journal of Personality and Social Psychology, 46(3), 610–620.
- Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). “On the Fragility of Skilled Performance: What Governs Choking Under Pressure?” Journal of Experimental Psychology: General, 130(4), 701–725.
筆者の簡単なプロフィール
ダーツ歴12年、PERFECTプロ歴3年。
ダーツの技術やバレルの特徴を調べるのが楽しみです!
実際に投げたバレルは400種類以上。(2022/3月現在)
数多くのレッスン受講歴あり、イップス・グリップイップスという経験から自身でも身体について勉強しています。